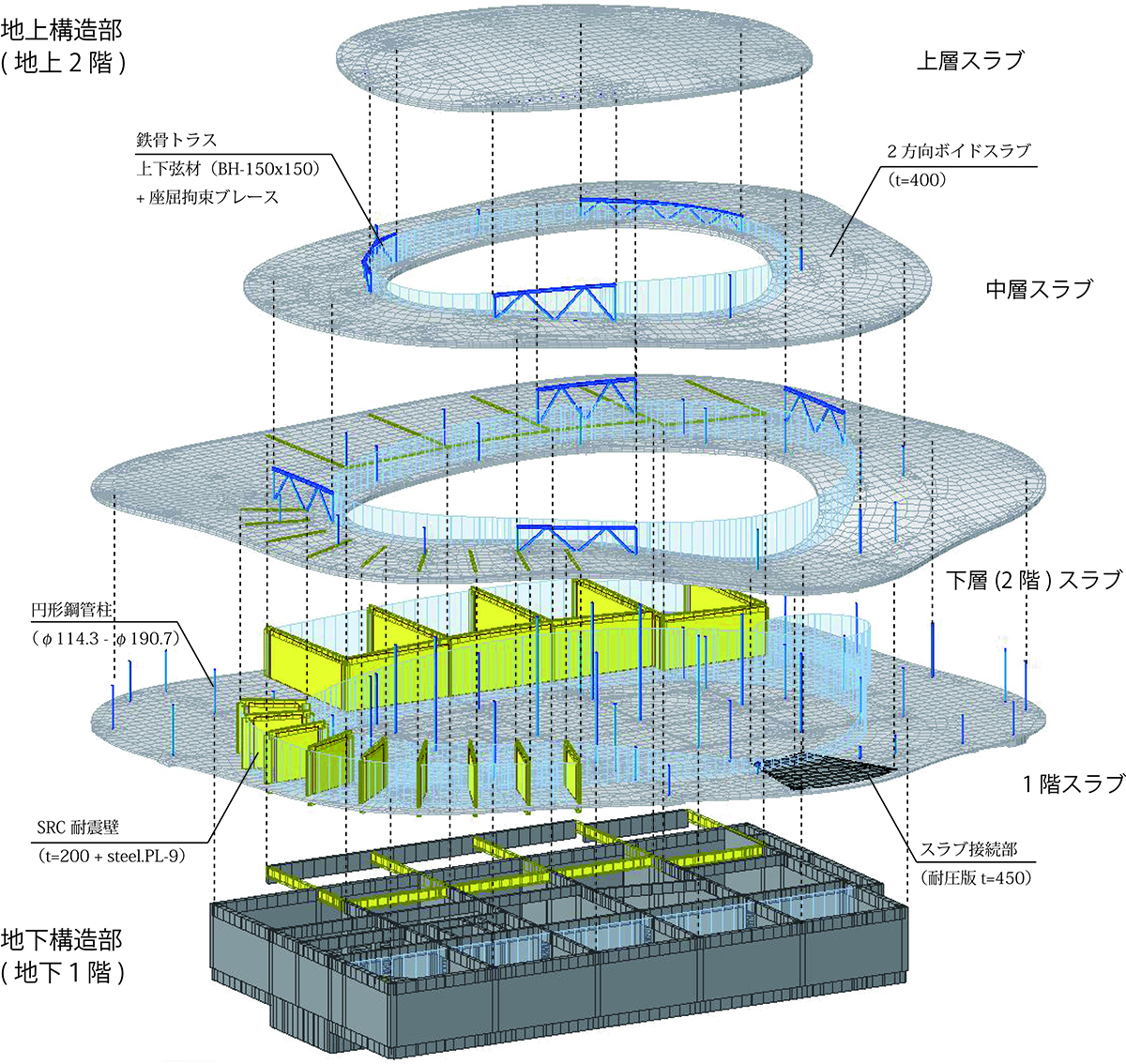犬飼研究室
担当教員 : 犬飼 基史
- 構造デザイン
- 構造設計
- 構造計画

担当教員 : 犬飼 基史
芸術と技術の統合により生み出される建築の美の追求と実現を目指します。
<技術と芸術(構造と意匠)の融合から生まれる建築の美>
昔から日本の建築は、地震、台風や大雨による風水害、大火災など各種の災害に悩まされてきました。構造の最も重要な役割は、そうした自然の力に抗って人命や財産を守ることにあります。しかし、「安全性の確保」は構造物や構造技術に課せられた必要不可欠な条件ですが、建築物として十分な条件ではありません。ちなみに古代ローマの建築家ウィトルウィウスが著した『建築論』には、建築の目標が簡潔に箇条書きされています。「強さ(firmitas)・用(utilitas)・美(venustas)」(森田慶一訳)これに設備を加えて、技術(構造+設備)と機能と美しさが基本的な建築要素だと考えると、現代における建築の理想とすべき要素としても十分に成立します。またこれらの要素は基本的には独立していますが、相互に強く関係し合っています。とくに建築の中で最も本質的、建築的である構造は、建物の機能や美しさにダイレクトに影響を与える決定的な要素でもあります。構造と美しさとの関係は表裏一体の関係にあり、構造の美しさが、建築の美しさの中核をなしているのです。しかし、そのような建築に対する美意識は、人によっても時代によっても極端に異なるため、絶対的な視座から「美」について語ることは大変困難だといえます。
元来、多摩「美」術大学(Tama Art University)の英語表記にもあるアート(Art)という言葉は、ラテン語のアルスが語源とされており、元来は技術と芸術の両方を意味していました。つまり従来の解釈においては「技術は芸術である」といえます。一方、建築の語源であるアーキテクネ(建築)のテクネは技術を、アーキテクト(建築家)のテクトは技術者を意味しており、接頭語のアーキはそれらを総括する偉大なもの、または人のこと指していました。つまり、建築の芸術はもともと建築技術を意味するものであったし、また逆に言えば建築の技術は建築芸術そのものでもありました。それが近代建築以降の分業にともない、芸術と技術は分化しましたが、そのような現代においても、芸術と技術の関係は基本的に成立します。
私の研究室では、建築の芸術と技術が弁証論的に統合されることで現実のかたちとなって生み出される建築の美の追求と実現を目指しています。